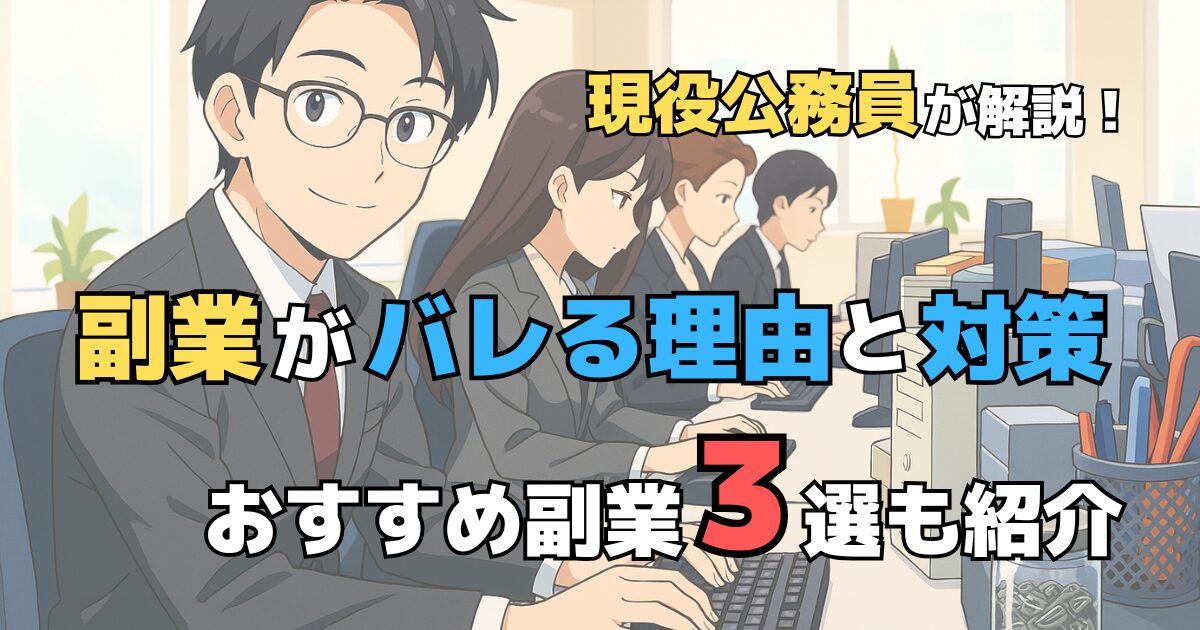「副業バレが怖くて行動に移せない。バレない方法はない?」
「収入を増やしたい!公務員に認められている副業はないの?」
2025年4月現在、公務員の副業は法律によって禁止されているのが現状です。とはいえ、副業で収入を得たい公務員は非常に多くいます。
私は約13年間、地方公務員として仕事をしていますが、いつの時代も「副業したい」という声はなくなりません。
そこで今回は
公務員の副業バレへの対策と公務員にも認められている副業
について解説していきます。
- 公務員の副業がバレる理由と対策
- 公務員に認められている副業3選
- 副業できなくてもスキルを磨く理由
公務員でも副業ができるのか知りたい人はぜひ最後まで読んでください。
公務員の副業がバレる理由
公務員の副業がバレる理由には以下のものがあります
- 住民税額の増加
- 同僚からの通報
- SNSやオンライン活動での顔バレ
一つずつ解説していきます。
住民税額の増加
副業が勤務先にバレる理由の大半が「住民税額の増加」です。
なぜ住民税額が増加すると職場に副業していることが分かってしまうのでしょうか?
住民税額の増加で副業がバレる基本的な流れはこのようになっています。
- 副業で収入が増える
- 住民税額が増加する
- 給与明細に数字が反映される
- 経理担当者が給与と税額が合わないことに気付く
住民税は前年の1月1日から12月31日までの総所得(本業+副業)に基づき算出されます。
本業の勤務先は、職員の代わりに住民税を納めていますが、給与から住民税を天引きするときに自治体から届く「住民税決定通知書」を参考にしています。
会社から支払われる給与以外に収入があると、住民税額が増え、経理担当者が「収入の割に住民税が高い?副業している?」と気付くわけです。
やっぱりバレずに副業をする方法はないかな?
住民税額の増加による副業バレ対策は「確定申告」
確定申告をすれば、住民税額の増加による副業バレを防ぐことができます。
会社員や公務員は自営業者と違い、自身で確定申告をする機会が少ないですが、副業バレを防ぐためには必須なので、覚えておきましょう。
人によって確定申告の内容に違いがあるため詳しいやり方は省き、重要なポイントだけお伝えします。
重要なポイントはコレだけです
特別徴収と普通徴収の違いは、住民税を勤務先が納めるか自分で納めるかだけです。
特別徴収と普通徴収の違い
簡単に特別徴収と普通徴収の違いを整理しておきます。
| 納める人 | 納税方法 | |
| 特別徴収 | 勤務先 | 給与から天引き |
| 普通徴収 | 個人 | 納付書で納税 |
普通徴収の場合、住民税の納付書は自宅に郵送されてくるため、勤務先に届くことはありません。
自分で住民税を納めるため、勤務先に「住民税額の増加」がバレることがありません。
勤務先には通常通り、本業の収入から計算された住民税額が知らされることになります。
副業としてアルバイトを選ぶのはアウト
副業をしたいからと「アルバイト」を選ぶのは厳禁です。
アルバイトを選んではいけない理由
- アルバイト先も従業員に支払った給料を自治体に報告している
- 副業中の現場を目撃されたら言い逃れできない
- 肉体労働の副業では時間と体力を奪われ、本業に支障が出る
「現金手渡しなら大丈夫」と聞きますが、アルバイト先も収益や経費(給与)も報告しているので、バレるリスクが高まります。
副業形態を選ぶときには、アルバイトやパートではなく、フリーランスや業務委託契約を選択する必要があります。
同僚からの通報
周辺住民から副業について通報されるケースは聞いたことがありませんが、同僚からの通報でバレるケースは多いです。
本業以外で収入を得られるようになると、つい自慢したくなるかもしれませんが、副業バレのリスクを高めてしまいます。
副業バレのリスクを徹底的に排除するため、以下のことに注意しましょう
- 勤務時間中の副業を厳禁とする
- 副業に関連する書類などを職場に持ち込まず、自宅で保管する
- 第三者に副業の存在を口にしない
職場で副業の話題は尽きませんが、会話には極力加わらないようにしています。
SNSやオンライン活動での顔バレ
SNSなどを活用した副業もありますが、絶対に顔バレしない工夫が必要です。
YoutubeやInstagramなど、どこで誰が見ているか分かりません。バレる可能性は低いかもしれませんが、ゼロではありません。
副業として選ぶことに問題はありませんが、バレないための対策を講じる必要はありますね。
副業バレが怖い公務員にもできる副業3選
ここからは本業以外に収入を得たいけど、副業バレは怖い公務員に向けて、オススメの副業をご紹介します。
おすすめの副業3選はコレ
- 株式投資
- 不動産投資
- フリマサイト
いずれの副業も始めるにあたって勤務先の許可は必要ありませんが、不動産投資に限っては規模が大きくなると兼業許可を得る必要があります。
取り組みやすいのは株式投資とフリマサイトです。
株式投資
2024年から新NISAが始まり、株式投資を始めた人も多いのではないでしょうか?
株式投資は、証券口座を開設すればすぐにでも始めることができます。
FXや暗号資産取引が話題になりがちですが、投機性(ギャンブル性)が高いのでオススメできません。
株式投資で得られる配当金は不労所得とも呼ばれ、その名のとおり持っているだけでお金を運んできてくれる存在になります。
公務員として注意すべき点は、インサイダー取引です。
担当する部署によって、企業の情報を得やすい立場にあるので注意する必要があります。
不動産投資
株式投資のようにすぐ始めることはできませんが、公務員ならではのメリットがあります。
- 収入が安定しているため銀行からの融資が通りやすい
- 倒産や解雇がないため、将来の支出を見据えた資金計画を立てられる
- 不動産投資にかかる費用を経費として一部計上できる
私は住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査では一度も断れたことがありません。
規模が大きくなると勤務先から兼業許可を取る必要があります。
不動産投資の場合、家賃収入が500万円以下または5棟10室という制限があり、これを超える場合は兼業許可が必要になります。
「必ずしも許可されるわけではない」ということは頭に入れておく必要があります。
フリマサイト
フリマサイトで不用品を販売するだけなら副業に該当しません。
私もフリマサイト「メルカリ」を使って、これまで90点以上の不用品を販売してきました。
売れるまでの時間に違いはあれど、出品したものはすべて売れています。
これまで出品したものには以下のものがあります
- 本、時計
- 機種変更前のスマホ
- サイズアウトした子ども服、靴
- ゲーム機本体とゲームソフト
- ぬいぐるみ、キーホルダー
- 車のタイヤとホイール
- プリントできなくなった壊れたプリンター
自分にとって不要になったものでも、必要と感じる人は意外と多いです。
副業収入を得られるわけではありませんが、割安で使えたと思えば良いですよね。
副業できなくてもスキルを磨く理由
未だ公務員の副業は認められていませんが、スキルを磨くのは自由です。
- 公務員の安定がいつ崩れるか分からない
- 年功序列制度が崩れつつあるから
- 公務員の業務ではスキルが育たないから
公務員の常識は世間の非常識と言われるほど、一般企業と公務員とでは認識に違いがあります。
公務員の転職が難しいと言われる理由に「スキルがない」ということが挙げられます。
私を含め、多くの公務員は今の職場以外でやっていける自信を持っていません。
だからこそお金を稼ぐためのスキルを身につける必要があると考えています。
公務員でもリスクを排除すれば副業できる
今回の記事では公務員の副業バレへの対策と公務員にも認められている副業について解説しました。
副業がバレる理由には以下のことがありました
- 住民税額の増加
- 同僚からの通報
- SNSやオンライン活動での顔バレ
副業がバレたときのリスクは大きいので、そこを理解した上で副業に取り組む必要があります。
また副業バレへの対策についても解説をしました
- 確定申告で「特別徴収」ではなく「普通徴収」を選ぶ
- 副業先として「飲食店のアルバイト」などを選ぶのはダメ
- 副業について絶対に口外しない
2025年1月24日、石破首相が「地方公務員の兼業・副業の弾力化」を表明し、公務員の副業解禁の流れが強まっています。
副業が解禁されれば、公務員のなり手不足も解消されるかもしれません。
良い波(公務員の副業解禁)が来たときに、「スキルが何もありません」と乗り遅れないよう、しっかりとスキルを磨いていきたいですね!